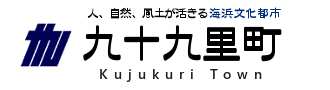個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税・県民税)を徴収(天引き)し、納入いただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、原則として給与を支払うすべての事業者は特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
事業主には個人住民税の特別徴収義務があります。事業者(給与支払者)の皆さんにおかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
1.給与支払報告書の提出
毎年1月31日までに給与支払報告書を市町村に提出することとなっています。給与支払報告書の未提出や虚偽の記載をした場合は、地方税法第317条の7において罰則規定が設けられています。
2.特別徴収税額の通知
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
特別徴収のしおりについて
個人住民税の給与からの特別徴収について、給与所得者の就職、退職等に伴う異動がある場合は、届出が必要です。届出に関する様式をまとめた特別徴収のしおりがありますので、ご活用ください。また、主な様式については、「様式等ダウンロード」からもご利用になれます。
個人住民税の特別徴収に関するQ&A
Q.特別徴収はしないといけないのですか?従業員も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが。
A.地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています(地方税法第321条の4および各市町村の条例)。したがって、対象となる従業員数が少ないことや、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行わないことは認められていません。
Q.特別徴収は何かメリットがあるのですか?
A.特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例の承認)
なお、個人住民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書等に基づいて市町村が行い、従業員ごとの個人住民税額を通知しますので、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになっています。
Q.新たに特別徴収により納税するためには、どんな手続きをすればいいのですか?
A.毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に『新規』または『特別徴収希望』と記載の上、各市町村にご提出ください。
5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。
特別徴収していた納税者が異動された場合
退職、休職等が生じたとき
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書に該当事項を記載して、異動のあった翌月の10日までに提出してください。
※翌年の1月1日から当該年度の4月30日までの間に退職または休職する人等に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務づけられています。
転勤、出向等が生じたとき
特別徴収に係る給与所得者異動届出書の上欄は転勤前の事業所等で記載し、転勤後の事業所に送付してください。転勤後の事業所は、受領した給与所得者異動届出書に必要事項を記載のうえ、当町に提出してください。
※異動届出書の提出がありませんと納付の確認ができなくなり、ご迷惑をおかけすることになりますので、異動が生じた場合は必ず異動届出書を提出してください。
特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知した後に、その特別徴収税額に誤りがあったり、またはこれを変更する必要が生じたときは『特別徴収税額変更通知書』を送付しますので、その通知書受理後からは変更された月割額により徴収してください。
納入場所
九十九里町指定金融機関
千葉銀行(取りまとめ店九十九里支店)
九十九里町収納代理金融機関
みずほ銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・銚子商工信用組合・銚子信用金庫・山武郡市農業協同組合・東日本信用漁業協同組合連合会・中央労働金庫
ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・山梨県および関東各県)
九十九里町役場出納室
納入書の取り扱いについて
特別徴収の納入書につきましては、OCR(光学文字読取装置)により数字を読み取りますので、次の点にご留意のうえお取り扱いください。
納入書には税額を印字してありますので、納入税額に変更がない場合、何も記入しないで納入してください。
変更がある場合のみ(退職・転勤・税額変更等)正しい納入税額を記入してください。
様式等ダウンロード
 特別徴収の事務手引き (ファイル名:tebiki.pdf サイズ:2.28 MB)
特別徴収の事務手引き (ファイル名:tebiki.pdf サイズ:2.28 MB)特別徴収の事務手引き
 特別徴収切替届出書 (ファイル名:kirikaetodoke2022.pdf サイズ:123.46KB)
特別徴収切替届出書 (ファイル名:kirikaetodoke2022.pdf サイズ:123.46KB)普通徴収から特別徴収への切替届出書
 給与所得者異動届出書 (ファイル名:idoutodoke2022.pdf サイズ:149.75KB)
給与所得者異動届出書 (ファイル名:idoutodoke2022.pdf サイズ:149.75KB)退職、休職、転勤等の異動があった場合の届出書
 所在地・名称変更届出書 (ファイル名:syozaichihennkou2022.pdf サイズ:143.58KB)
所在地・名称変更届出書 (ファイル名:syozaichihennkou2022.pdf サイズ:143.58KB)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
 納期の特例申請書 (ファイル名:noukitokurei31.xls サイズ:38.50 KB)
納期の特例申請書 (ファイル名:noukitokurei31.xls サイズ:38.50 KB)従業員が10人未満の事業所は、申請により納期を年2回とすることができます。
お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!