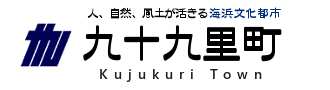住民税とは
町民税と県民税を合わせて一般的に住民税と呼ばれています。また、住民税は個人の住民税(個人町(県)民税)のほか、法人の住民税(法人町民税)もあります。
個人町(県)民税
個人町(県)民税は、一定額を課税する均等割と、所得金額に応じて課税する所得割の2つの合計金額によって算定されます。なお、町民税と県民税とを合わせて徴収されます。
◎個人町(県)民税の納税義務者
| 納税義務者 | 均 等 割 | 所 得 割 |
|---|---|---|
1月1日に町内に住所がある人 | ◎ | ◎ |
九十九里町内に住所を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
1月2日以降に他市町村に住所を移しても、その年の住民税は九十九里町で課税されます。
◎課税されない人
●均等割も所得割もかからない人
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入では、年収204万3千円未満)の人
●均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合)+10万円
●所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合)+10万円
◎税額の計算
個人町(県)民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を基に、1月1日現在居住している市町村に納める税金です。
●均等割(定額)
町民税 3,000円
県民税 1,000円
※この他に国税として森林環境税 1,000円が課税されます。森林環境税については「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご覧ください。
●所得割
所得割額の計算方法
所得金額-所得控除額=課税総所得金額
課税総所得金額×税率-税額控除=所得割額
税率は、町民税6%、県民税4%です。
個人町(県)民税の申告
●申告書を提出しなければならない人
- 1月1日現在、九十九里町内に住所があり、前年中に事業所得(営業、農業など)、利子所得、配当所得 、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、および山林所得のあった人
- 給与所得者で次のa~fに該当する人
a.勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人
b.給与所得以外の所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下の人は所得税の確定申告をする必要がないこととなっていますが、町(県)民税は必要となりますのでご注意ください。)
c.2カ所以上から給与の支払いを受けている人
d.前年中に退職した人
e.給与収入が2,000万円を超える人
f.同族会社の役員などで、その会社などから給与所得の他に貸付金の利子や不動産の使用料の支払いを受けている人
●申告書を提出しなくてもよい人
- 所得税の確定申告をした人
- 給与所得のみの場合で勤務先から給与支払報告書が提出されている人
※提出されているかどうか不明な場合は勤務先にご確認ください。
●所得がなかった場合の申告について
所得がなかった場合でも、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の適正な算定ができなくなりますので、必ず申告書を提出してください。申告書の提出がない場合には、国民健康保険税の軽減などが適用されなかったり、各種証明類の発行ができない場合がありますのでご注意ください。
※町(県)民税申告書の裏面に所得のなかった人の記入欄がありますので、必要事項を記入し、提出してください。
個人町(県)民税の納税方法
個人の町(県)民税の納税方法は、次の3つの方法があります。
※事業・給与・年金など、複数の種類の所得のある方は、3種類の納税方法となる場合があります。
普通徴収(納付書や口座振替での納付)
町から送付する納税通知書(納付書)により、金融機関などの窓口で直接納付する方法です。
納税には、口座振替がご利用いただけます。
納期限 6月末、8月末、10月末、翌年1月末の計4回 (注意)納期限が土・日・祝日にあたるときは翌日になります。
給与からの特別徴収
勤務先から支払われる給与から毎月(6月から翌年5月までの12回)天引きし、勤務先が町に納付する方法です。
納期限 各月の翌月10日
公的年金からの特別徴収
公的年金の所得にかかる個人町(県)民税額を、支給される公的年金(仮徴収:4・6・8月、本徴収:10・12・翌2月)から天引きし、年金支払者が町に納付する方法です。
原則、4月1日に公的年金を受給している65歳以上の方が対象ですが、次にあてはまる方は除かれます。
1.介護保険料が年金から特別徴収されていない方
2.特別徴収される年金から、介護保険料や後期高齢者医療保険料などを差し引いた残りの額が特別徴収される個人町(県)民税額以下となる場合 など
新規に公的年金からの特別徴収が開始される方は、10月支給分の公的年金から特別徴収が始まるため、公的年金所得にかかる年税額の2分の1相当額については、6月と8月に普通徴収の方法により納付していただくことになります。
2年目以降の場合は、仮徴収として前年度の公的年金にかかる個人町(県)民税額の2分の1相当額を4・6・8月の3回に分けて公的年金から特別徴収されます。また、10月以降の本徴収では、当該年度の公的年金にかかる個人町(県)民税額から仮徴収された額を引いて残った額を10・12・翌2月の3回に分けて公的年金から特別徴収されます。
お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!